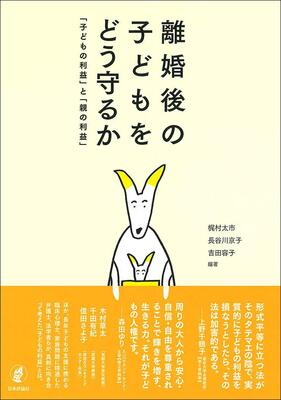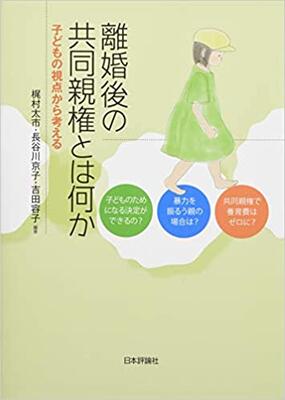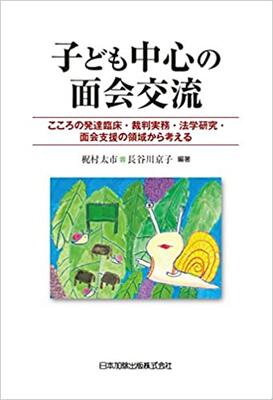書籍紹介
書評 梶村太市・長谷川京子・吉田容子編著 『離婚後の子どもをどう守るか 「子どもの利益」と「親の利益」』(渡辺義弘)
渡辺義弘先生による、書評 梶村太市・長谷川京子・吉田容子編著『離婚後の子どもをどう守るか 「子どもの利益」と「親の利益」』の紹介です。
全文を読むことができます。
1.はじめに
本書は、同じ編著者が世に問題提起する三部作の完結編である。
三部作を貫くテーマは、離婚後の子どもの監護をめぐる「子どもの利益」の追求と解明である。
そして、三冊目の本書は、いよいよ、「子どもの最善の利益」の内実に焦点を絞る。
本書の特徴は、学問と実務の両面から現実を照射する。それは次の2つの実践を励ます。
第1は、「離婚後共同親権法則」の立法化が、父母の高葛藤紛争の現実からいかに遊離しているかを世論に訴える実践である。
第2は、家庭裁判所実務が採用する面会交流原則的実施政策を、具体的紛争の中で苦悩しつつ
比較基準方式に転換を求める監護親たちの実践である。
以下、本書の内容を章の順序に、私見により紹介し、若干の論評をする。
書評の全文はこちらをどうぞ。コンパクトな要約も記載されています。
書評 梶村太市・長谷川京子・吉田容子編著『離婚後の共同親権とは何か : 子どもの視点から考える』(渡辺義弘)
渡辺義弘先生による、書評 梶村太市・長谷川京子・吉田容子編著『離婚後の共同親権とは何か : 子どもの視点から考える』の紹介です。全文を読むことができます。
1 .はじめに
昨年 7 月の新聞報道により、父母が離婚しても、双方が子どもに対し共同親権を持つ法制の導入問題が突如浮上した。そのための民法改正の検討方針を、上川法務大臣(当時)が記者会見で表明した。法制審議会への諮問は予断を許さない。
しかし、この「離婚後共同親権」法制を採用している先進諸国においても、この制度は曲がり角ともいうべき苦悩の中にある。その導入は、はたしてわが国の家事司法、とりわけ紛争家族にどのような影響を及ぼすのだろうか。
本書は、紛争家族の目線で、この法制の導入に「危うさ」を実感している学者と弁護士たちが、正面からこの法制に対決して論じた初めての論文集である。各論文はいずれも、事実と執筆者の体験に基づき、法制導入に対する警告の主張と理論を展開している。
法制を推進しようとする側は、誠実に対応する限り、これらの主張と理論を一つ一つ論破しない限り、国民に対して説得力を持たないと考える。立法化は、これらの主張を無視して進められるのだろうか。以下、本書の内容を章の順に、紹介ないし論評したい。
離婚後の子の監護と面会交流 子どもの心身の健康な発達のために
梶村太市・長谷川京子・吉田容子編著『離婚後の子の監護と面会交流 子どもの心身の健康な発達のために』の紹介です。
内容紹介
面会交流原則実施の弊害、共同監護の問題点を明らかにし、子の心身の健康な発達にかなう制度運用のための方策を具体的に検討する。
目次
はしがき
◆序論/社会学者・精神科医からの問題提起
第1章 家族紛争と司法の役割──社会学の立場から
………………………………………………………………千田有紀
第2章 子どもの発達と監護の裁判
──科学的検討・外部臨床家との連携・検証
………………………………………………………………渡辺久子
◆新たな課題/裁判の争点から
第3章 「松戸100日面会裁判」が投げかける問い…………安田まり子
◆課題の検証と対策/あるべき監護法制のために
第4章 非監護親との接触は子の適応に必要か有益か
……………………………………………………………長谷川京子
第5章 「片親引き離し/症候群」批判……………………長谷川京子
第6章 フレンドリー・ペアレント・ルールは子どもを害する
………………………………………………………………可児康則
第7章 司法は面会交流殺人から子どもと監護親を守れるか
………………………………………………長谷川京子・吉田容子
第8章 面会交流支援の実情と限界…………………………吉田容子
第9章 面会交流の弊害から子どもを守るための調停・審判のあり方
──面会交流原則実施論と第三者支援の理論的破綻と実際的危険性
………………………………………………………………梶村太市
第10章 離別後の子の監護に関する考え方――欧米の経験を参考に
………………………………………………………………小川富之
第11章 「親子断絶防止法」の立法化がもたらす危惧は何か
………………………………………………………………渡辺義弘
あとがき
離別後の親子関係を問い直す 子どもの福祉と家事実務の架け橋をめざして
小川富之・ 高橋睦子・ 立石直子編 『離別後の親子関係を問い直す 子どもの福祉と家事実務の架け橋をめざして』の紹介です。
【内容】
離別後の親子関係は、「子の利益」となっているか。子の発達の課題やリスクを心理学・脳科学・乳幼児精神保健等の知見をもとに精査し、親子の交流を推進する昨今の家事紛争に法学と実務の立場から検証・提言。
【はしがき】
はしがき
日本では、近年、離婚後の子どもと別居親の交流に関心が高まっている。離婚に際して、父母が子どもの養育について協議する事項として、子どもと同居して養育する親(監護者)に加え、養育費と面会交流が明示され、両親は、子どもの最善の利益を尊重しつつ、これらについて協議することとされている。離婚後も子どもが双方の親と人間関係と交流を維持することで子の適応が高まるという期待のもとに、家族法学の研究においては、離婚後の子どもと別居親の関わりについての議論が盛んである。また、家庭裁判所での司法実務においても、子どもと別居親との面会交流の促進には積極的である。
面会交流のメリットについての議論では、子どもの養育や親子関係の維持について、両親が離婚後も引き続き共同で取り組むことを基本的な理念として、離婚後の「あるべき家族像」が論じられている。 父母のパートナー関係が破綻していても、子どもの最善のために、大人らしく「親として適切」な言動がなされることを前提として、子どもの養育に関する父母間の協議が求められる。
別居親には面会が認められ、同居親には子の面会を受忍しその実現に協力する義務が設定される。 しかし、「子どもの別居親との関わり」では、別居親の望みは賛同・支持が得られやすい一方、同居親は別居親の望みをかなえることが義務として課されるという、非対称な構造についての問題提起はほとんど聞かれない。
また現実にも、離婚前後の親たちはどの程度、子どもの養育や面会交流について冷静に話し合えているのだろうか。子どもとの面会を求める別居親は皆、面会の場面や面会をめぐって、「親として適切」な言動、振る舞いをするという推定が所与の前提とされがちである。
離婚する家族にこの「あるべき家族像」は一律にあてはまるだろうか。
結婚の枠組みでの共同生活を続けられなくなった父母が、「あるべき家族像」の理念に添うように、協議によって子の最善に適う解決を常に見いだせるだろうか。父母間では協議できず、紛争の解決を裁判所に持ち込むような状況において、親子関係の交流・維持を推進し「あるべき家族像」に近付けるようにすることで、現実の紛争について適切な解決を導き、肝心の子どもの安全を守れるだろうか。
日本の制度のもとで、家族による話し合いが順調に進まない、困難をかかえる離婚について調整役を担う主な専門家は(福祉セクターではなく)司法・家庭裁判所(裁判官、調査官、調停委員)や弁護士たちである。したがって、家庭裁判所には、高葛藤事案が高い確率で持ち込まれる。その司法において面会交流の促進が主流化されていることは、高葛藤事案での面会交流をめぐる紛争の解決
においても、面会交流の促進へと方向づける。
さらに、高葛藤事案にせよ、高葛藤が顕在化しない事案にせよ、一体どれほどDV・虐待があるのだろうか。 日本の離婚の 9 割程度を占める協議離婚についても、高葛藤事案についても、DV・虐待の実態は十分に把握されていない。全体像の把握もままならい状況下で、専門家・実務家たちの問題認識、つまり、DV・虐待そのものの問題の理解度にも大きなばらつきがある。DV・虐待の本質ともいえる強制的な「支配とコントロール」が離婚前からパートナー関係・家族関係に影を落としてきた場合には、面会交流の制度は離婚後もそのコントロールを維持する手段になりうるリスクがある。
DV・虐待についての専門家の感度が低ければ、重篤なDV・虐待が絡む事案であっても被害者側の声は必ずしも傾聴されない。 むしろ「子どものため」には、大人の事情やニーズを制限してでも、親子関係の維持が最優先される可能性がある。理念、規範そして現実に向き合う実務の現場は、専門領域のベクトル(方向性)に整合性がなければ、流動的な家族関係の調整や子の最善の達成は実現困難な夢に終わる。少なくとも、子どもの健全な安定的発達にとって破壊的な悪夢は避けなければならない。
日本では別居親からの面会交流の申立件数が2000年代に入って急増している。しかし面会交流について別居親が強く積極的に要求し裁判も辞さないまでになったという社会現象そのものをどう解釈するか、十分に議論や分析が深まっているとはいえない。ジェンダー平等と子どもの発達の関連についての理解がなければ、面会交流における同居親と別居親の非対称性の問題も看過される。
近年、裁判所の面会交流に対する姿勢は、子どもの安定的な養育環境の維持から、別居親との面会交流を積極的に促進する方向性へ急旋回している。離婚後に、一方の親と同居し養育されている子どもにとって、別居親との関わりを増進することが常に子どもにとっての最善なのかという点も、議論は深められてはいない。それでも、日本の法制度を改正するべきだという議論や家庭裁判所の面会交流の処理実務は、急速に進んでいる。
本書は、「子の最善の利益」の本来の主役である「子ども」の発達の課題やリスクを乳幼児精神保健、心理学、子どもの発達・脳神経研究の知見をもとに精査し、上述のような日本での展開、課題および展望について、法学と司法実務の見地から検証・考察するものである。
謝辞:本書は、JSPS科研費25301044の助成を受けた研究の成果報告の一部である。
編者を代表して
髙橋睦子
子ども中心の面会交流―子どものこころの発達臨床・法律実務・研究領域から原則実施を考える
梶村太市・長谷川京子 著 『子ども中心の面会交流―子どものこころの発達臨床・法律実務・研究領域から原則実施を考える』の紹介です。
立場や見解の異なる各分野スペシャリト18名が執筆
面会交流の原則実施 の問題点・課題点に鋭く切り込む
【内容】
子ども中心の面会交流
こころの発達臨床・裁判実務・法学研究・面会支援の領域から考える
【児童精神科医、臨床心理士、研究者、弁護士、元裁判官が、面会交流の現状を問う】
・面会交流原則的実施政策の問題点 … 長谷川京子(弁護士)
・子どもの本音・声を歪めない面会交流とは?─乳幼児精神保健学からの警鐘─ … 渡辺久子(乳幼児・児童思春期精神科医)
・DVと離婚,子どものトラウマへの配慮と面会交流 … 田中究(児童精神科医・兵庫県立光風病院院長)
・片親引離し症候群PASと片親引離しPA─研究レビュー─ … ジョアン・S・マイヤー(弁護士/ジョージワシントン大学法科大学院特任教授)
訳・監修 髙橋睦子(吉備国際大学大学院社会福祉学研究科教授)
・児童虐待(不適切な養育)に陥った親と児童との面会交流の実情について … 岩佐嘉彦(弁護士)
・離婚後の親子の交流と親権・監護・親責任 … 小川富之(福岡大学法科大学院教授)
・DV・児童虐待からみた面会交流原則的実施論の課題 … 水野紀子(東北大学法学研究科教授)
・臨床心理士,面会交流援助者からみた面会交流原則実施論 … 山口惠美子(公益社団法人家庭問題情報センター常務理事/臨床心理士)
・心理学的知見の教条化を排した実務運用はどうあるべきか─子ども中心の面会交流の背景を踏まえて─ … 渡辺義弘(弁護士)
・原則実施論の問題点 … 斉藤秀樹(弁護士)
・面会交流をめぐる家裁実務の問題点─調査官調査の可視化を中心に─ … 可児康則(弁護士)
・取り残される子どもの気持ち … 安部朋美(弁護士)
・弁護士代理人からみた面会交流実施の問題点について─「子ども中心」とは何か,原則実施論の条件作り─ … 西片和代(弁護士)
・DVと面会交流 … 秀嶋ゆかり(弁護士)
・原則的面会交流論の問題性─元裁判官の立場から─ … 坂梨喬(弁護士/元福岡家庭裁判所・地方裁判所判事部総括)
・面会交流調停・審判の運用はどのようになされるべきか─やや随想的に(元裁判官の感想的意見)─ … 森野俊彦(弁護士/龍谷大学法科大学院特任教授/元福岡高等裁判所部総括判事)
・家事紛争解決プログラムの意義─面会交流原則論とは何か─ … 大塚正之(弁護士/早稲田大学法学学術院招聘研究員/元千葉家庭裁判所判事)
・第三者機関の関与と面会要領の詳細化の諸問題─平成25年の二つの東京高裁面会交流決定をめぐって─ … 梶村太市(弁護士/常葉大学法学部教授/元横浜家庭裁判所部総括判事)
座談会 面会交流は原則的に実施できるのか
目次
第1章 長谷川京子
面会交流原則的実施政策の問題点
第1 子どもの幸せのための面会交流
第2 離婚に至る家庭の子どもの否定的な体験──父母の争い・暴力の被害と目撃
第3 面会交流が子どもの福祉にかなうための要件
第4 裁判に持ち込まれる事案
第5 原則的実施政策が子ども・監護親・非監護親の関係にもたらす結果
第6 先進国の経験
第7 おわりに
第2章 渡辺久子
子どもの本音・声を歪めない面会交流とは?
─乳幼児精神保健学からの警鐘─
第1 離婚にいたる子どもの否定的体験
第2 子どもが面会交流を拒否するとき
第3 家庭裁判所におけるドメスティックバイオレンス(DV)への対応
第4 子ども中心の面会交流のために 34
おわりに
第3章 田中究
DVと離婚,子どものトラウマへの配慮と面会交流
第1 はじめに
第2 事 例
第3 子どものトラウマ関連障害に関する診断基準
第4 トラウマ体験の子どもへの影響
第5 まとめ
第4章 ジョアン・S・マイヤー(Joan S. Meier)
訳・監修 髙橋睦子
片親引離し症候群PASと片親引離しPA
─研究レビュー─
第1 片親引離し症候群・PAS
第2 片親引離し・PA
第3 PA・PASと裁判所の判断
第4 片親引離し・PAとDVのつながり─ PAのパラダイムの逆転
第5 専門機関や専門家とPAS・PA
第6 訴訟当事者にとっての戦略的課題─ 具体的な事例において
第7 「片親引離し」(PA)の主張への対処:虐待を看過しないアプローチ
第5章 岩佐嘉彦
児童虐待(不適切な養育)に陥った親と児童との面会交流の実情について
第1 児童虐待ケースと親子の関係性について
第2 面会交流の制限が問題となる場面
第3 親子が分離されている場合の面会交流の制限について
第4 面会通信制限の要件について
第5 児童福祉の対応からみたいわゆる「原則面会」論の問題点
第6章 小川富之
離婚後の親子の交流と親権・監護・親責任
第1 はじめに
第2 諸外国における別居・離婚後の子の養育について
第3 日本の制度を考える上で必要なことは
第4 おわりに
第7章 水野紀子
DV・児童虐待からみた面会交流原則的実施論の課題
第1 日本家族法と家庭内暴力
第2 家庭内暴力と親権の行方─最高裁判例に現れたDVケース─
第3 子の奪い合い紛争への介入の難しさ
第4 介入の手段と方向性
第8章 山口惠美子
臨床心理士,面会交流援助者からみた面会交流原則実施論
第1 はじめに
第2 援助現場における最近の状況
第3 子ども中心の面会交流実現のための民間機関の実践
第4 課題と展望
第9章 渡辺義弘
心理学的知見の教条化を排した実務運用はどうあるべきか
─子ども中心の面会交流の背景を踏まえて─
第1 はじめに
第2 紛争の実質と原則的実施論の出現
第3 原則的実施論の理念把握の核心─その心理学的知見─
第4 原則的実施論の方針の核心─一元的な特段事情の苛酷な絞り込み─
第5 関連する諸問題
第6 結びに代えて─裁判所自身による再検討と追跡調査を─
第10章 斉藤秀樹
原則実施論の問題点
第1 序 論
第2 面会交流原則実施論の問題点(理論面)
第3 原則実施論の弊害
第4 非監護親へのメッセージ
第11章 可児康則
面会交流をめぐる家裁実務の問題点
─調査官調査の可視化を中心に─
第1 はじめに
第2 DV事案につき原則的実施論に基づき解決を図ることの危険
第3 家庭裁判所調査官による調査の可視化の必要性
第4 おわりに
第12章 安部朋美
取り残される子どもの気持ち
第1 面会交流は誰のため?
第2 子どもの意思は尊重しなくていいのか?
第3 面会交流を円滑に実施するためには
第4 面会交流義務とは?
第5 面会交流は子どもの健全育成のためのものである
第13章 西片和代
弁護士代理人からみた面会交流実施の問題点について
─「子ども中心」とは何か,原則実施論の条件作り─
第1 原則実施論における「事情」の考慮
第2 原則実施論が妥当する「時期」かどうか,紛争段階の見極め
第3 原則実施論が妥当する「目的」による申立てか否かの見極め(特にDV事案)
第4 子どもを中心としてニーズを捉えること
第5 事後的な検証可能性の確保
第6 最後に
第14章 秀嶋ゆかり
DVと面会交流
第1 はじめに
第2 DV事案と面会交流(総論)
第3 DVと面会交流(各論)
第15章 坂梨喬
原則的面会交流論の問題性
─元裁判官の立場から─
第1 原則的面会交流論とは何か
第2 原則的面会交流論のどこが問題なのか
第3 面会交流請求権の権利性
第4 家庭裁判所と原則的面会交流論
第16章 森野俊彦
面会交流調停・審判の運用はどのようになされるべきか
─やや随想的に(元裁判官の感想的意見)─
第1 はじめに
第2 面会交流権は実体的権利か
第3 「面会交流は原則的になされるべきである」か,どうか
第4 面会交流調停事件の運用について
第5 面会交流審判事件の運用について
第17章 大塚正之
家事紛争解決プログラムの意義
─面会交流原則論とは何か─
第1 はじめに
第2 臨床法学としての家事紛争解決プログラム
第3 面会交流原則論の意味
第4 面会交流を困難にする要因分析
第5 面会交流を妨げる要因を除去する方法
第6 面会交流合意形成システムの構築
第7 まとめ
第18章 梶村太市
第三者機関の関与と面会要領の詳細化の諸問題
─平成25年の二つの東京高裁面会交流決定をめぐって─
はじめに
第1 東京高決平成25年6月25日(第一決定)
第2 東京高決平成25年7月3日(第二決定)
第3 両決定の問題点
座談会 面会交流は原則的に実施できるのか